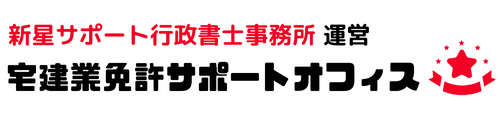【宅建業免許】保証協会とは? 入会の手続はどうすればいい?

宅建業を営むためには、宅建業の免許申請をして許可を受ける必要があります。しかし許可が下りて免許証が交付されても、それだけではまだ営業を開始することはできません。
宅建業を開始するためには、営業保証金を供託するか保証協会へ入会しなければなりません。
したがって供託か保証協会への入会のどちらかを選択することになりますが、保証協会への入会を選んだ場合、どのよな手続きが必要になるのでしょうか? また、そもそも保証協会とはどのような組織なのでしょうか?
この記事では、保証協会について、保証協会への入会の手続について解説させていただきます。
【宅建業免許】保証協会とは?
では、まずは保証協会とはどのような組織なのか見ていきましょう。
保証協会とは、宅建業を営む上で生じた「債権の弁済」や苦情の解決、研修などを行う社団法人のことです。ここでいう「債権の弁済」とは、トラブルなどで損害が発生したときに、営業保証金の範囲内で弁済を行うということをいいます。
このように保証協会に入会することで、宅建業で生じる金銭の問題を保障してもらえます。
保証協会は2つあります。全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会の2つで、それぞれの保証協会のロゴマークから前者を「ハト」後者を「ウサギ」という名称でも呼ばれています。どちらを選択するかは自由です。
保証協会へ入会するメリット
この記事の冒頭で、宅建業の営業を開始するためには、供託か保証協会へ入会することのどちらかを選択しなければならないと述べました。では、供託ではなく保証協会へ入会するメリットはあるのでしょうか?
保証協会へ入会するメリットは、供託と比べると初期費用が抑えられる点です。
供託の場合は営業保証金として、本店は1,000万円、支店は500万円を供託する必要があります。
保証協会へ入会する場合は、弁済業務保証金分担金として本店は60万円、支店は30万円の納付ですみます。供託と保証協会の金額を見比べると、保証協会のほうが初期費用を抑えられることは一目瞭然です。
ただし保証協会へ入会するために、弁済業務保証金分担金以外に保証協会への入会金も必要になりますが、それらを含めても供託よりも初期費用はかかりません。(※本店のみの場合、入会金込で約120万円くらいです)
このようなメリットがあるため、供託ではなく保証協会へ入会する事業者は多く存在します。
保証協会へ入会する手続
保証協会がどのような組織なのかが分かったところで、次は保証協会に入会するには、どのような手続きが必要になるのかを見ていきましょう。
入会する手続の流れ
保証協会への入会する手続の流れは次のとおりです。
※2つの保証協会で細かなところは異なるため、おおまかな流れになります。
- ①行政庁に宅建業の免許申請
- 保証協会へ入会の手続をする前に、行政庁に宅建業の免許申請をおこないます。
- ②保証協会へ入会に必要な書類を提出
- 入会に必要な書類を作成して、保証協会へ提出します。
- ③保証協会の審査
- 保証協会が入会資格の審査や事務所の調査などを行います。
- ④弁済業務保証金分担金、入会金等の振込
- 入会資格の審査後、弁済業務保証金分担金、入会金等の振込をします。
- ⑤営業開始
- 行政庁から宅建業の免許証を交付されたら、営業開始です!
入会する手続は上記のような流れになります。
③の審査は、保証協会や支部ごとに多少の違いがあり、面談を行う場合などもあります。
④の振込のタイミングも、審査前であったり審査後であったり異なりますので、正確な流れを知りたい方は保証協会にお問い合わせください。
入会に必要な書類
入会に必要な書類は、2つの保証協会で異なるところはありますが、入会申込書を含めておおよそ10種類ほどの書類が必要になります。
どちらの保証協会でも、ホームページからダウンロードできるようになっています。
入会に必要な費用
入会に必要な費用もやはり2つの保証協会で異なりますが、入会金や弁済業務保証金分担金、またその他の費用をあわせて、おおよそ120万円くらいです。
お得になるパッケージプランなどもあるので、2つの保証協会の入会に必要な費用を比較してみるのもいいかもしれません。
まとめ
保証協会のことや保証協会への入会の手続について解説させていただきました。疑問は解消されたでしょうか?
保証協会は2つ存在すること、入会する保証協会は自由に選択できること、また保証協会に入会する手続についてご理解いただけたかと思います。
2つの保証協会はどちらも入会することで、宅建業で生じる金銭の問題などを保障してもらえます。しかし入会の手続や費用などがやや異なるところもあるので、詳しく知りたい方は入会を考えている保証協会にお問い合わせされることをおすすめします。